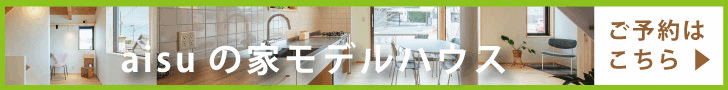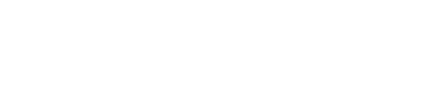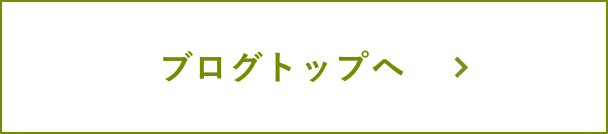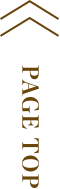和合町で進んでいる「aisuの家」
窓もつき、外壁の下地が進んでいます。

「aisuの家」の裏には、無数の“見えない工夫”が隠れています。
その一つである電気配線の工事について取り上げます。
暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。
4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。
(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)
aisuの家では、構造表しをベースにした空間が特徴です。

梁や柱の構造材をそのまま見せることで、暮らしの中で木構造のワクワク感を感じることができます。
しかし、この“構造を見せる”設計では、電気配線の取り回しに課題が出ます。
構造をそのまま見せると、天井裏が確保しにくく、電線を通すルートが限られてしまうのです。
そのため「aisuの家」では、水まわりの上に限定的に天井を設け、配線スペースとする工夫をしています。

手前が、構造をみせる部分。奥側が天井を張る部分。
一軒の家でも、多くの電気の線が張り巡っています。
天井だけではありません。
壁内の配線についても、工夫があります。
通常、電気配線は断熱材の中を通すことが多く、その分、断熱材の充填が疎かになるリスクや、防湿シートの施工が複雑になる場合があります。
aisuの家では、断熱材の施工を優先し、その後で配線できるように、内壁側に“胴縁(どうぶち)”を施工する工夫をしています。

この“ひと手間”によって:
- 断熱材をすみずみまでしっかりと充填できる
- 防湿シートの破れや施工ミスを減らせる
- 安全かつスムーズに配線できる
「断熱材施工性」と、「電気配線のしやすさ」が同時に叶う仕様を標準としています。
構造を表す空間を採用しながら、断熱性・気密性・電気配線のしやすさを確保するには、設計と施工の連携が不可欠。
aisuの家では、使用する素材だけでなく、施工方法の細部まで、設計段階から検討しています。
それによって、構造の魅力を活かした空間と住宅としての性能の、どちらも大切にした家づくりが可能になるのです。
aisuの家モデルハウスは夜7時まで見学受付中↓